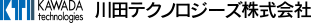TCFD提言に基づく情報開示
TCFD提言に基づく情報開示
最終更新:2025年6月23日
私たちKTI川田グループは、グループ理念である『安心で快適な⽣活環境の創造』のもと、グループ各社が展開する事業戦略と⼀体化したサステナビリティ課題への取り組みを推進しています。そしてまた『⼋⽅よし』(※)の精神に則り、すべてのステークホルダーとの対話や共創を通じて、「持続可能な社会の実現」と「グループの持続的な成長」を目指しています。
国際連合「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑えられない場合、異常気象や生物多様性の損失などのリスクが大きく高まると警鐘を鳴らし、その実現のためには温室効果ガス排出量を2035年に2019年比で60%減らす必要があると提言しています。当社グループは、重要課題(マテリアリティ)として「地球環境への貢献」を掲げ、その重点課題として「気候変動問題への積極的な貢献」を設定しています。地球温暖化を含む気候変動問題は、当社グループのステークホルダーを含めて、この地球に暮らす全ての人びとにとって、喫緊の課題となっています。
2023年6月、当社グループは、TCFD(※)提言への賛同を表明し、気候変動問題への取り組みとTCFDの提言に沿った情報開示を進めるとともに、気候変動に関するリスク・機会に適切に対応し、「カーボンニュートラル社会の実現」と「中長期的な企業価値の向上」を目指しています。
- ※「八方よし」とは、近江商人の心得と言われる「三方良し」を独自さらに拡張しステークホルダー全てに利をもたらす企業グループを目指すという考え方です。
- ※TCFDとは、「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称で、G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、2015年12月に金融安定理事会(FSB)により、気候関連問題に関する情報開示及び気候変動への金融機関の対応を検討するために設立されました。TCFDは、気候関連問題を適切に評価できるような一貫性、比較可能性、信頼性、明確性をもつ、効率的な情報開示を促す提言を策定することを目指して議論を重ね、2017年6月にTCFD提言を公表しました。
ガバナンス
取締役会の諮問機関として、サステナビリティ推進委員会を設置しています。委員長は取締役であるサステナビリティ推進室長が務め、取締役会が選任する委員で構成されます。委員会は原則として毎月開催され、同委員会の下部組織として当社グループ各社の総務部長等をメンバーとしたサステナビリティ推進会議、さらにその下部組織として当社グループ各社のサステナビリティ推進委員会が存在します。これらの委員会への指示・諮問に対する報告・答申に基づき、気候変動を含む幅広いサステナビリティ課題について、その相互関連性などを含めたリスクや機会を議論し、対応策を検討し、定期的または必要に応じて取締役会に報告・答申を行います。
取締役会は重要な方針や課題についての審議・決定を行い、その後、サステナビリティに関するさまざまな活動の内容や進捗状況等についてモニタリングを行います。また、指揮・監督の責任も担い、サステナビリティへの取り組みがサプライチェーンを含めて適切に進められているかを確認します。
このように、取締役会並びにサステナビリティ推進委員会がそれぞれの役割分担を通じて、そしてそれらが有機的な連携を行うことで、サステナビリティ経営を着実に推進しています。

戦略
当社グループは、気候変動問題をリスク・機会の両面で捉えており、非常に重要な社会課題と認識しています。そして、移行リスクについては1.5℃以下シナリオ(※)、物理的リスクについては4.0℃シナリオ(※)を活用し、主に2030年代までを中心に、事業への影響度を勘案し、当社グループの全ての事業を対象にリスク・機会を検討・分析しました。以下に特定したリスクと機会を示します。

また、移行リスクと物理的リスクの財務的なインパクトの算出を行いました。以下にその内容を示します。
- ※1.5℃以下シナリオ
2050年までに地球規模で温室効果ガス排出量ゼロを実現する規範的シナリオ。
政策、エネルギー・産業構造、資源価格等は、IEA「World Energy Outlook2024」の「NZE2050シナリオ」、平均気温等気候変動に関する想定は「IPCC第6次評価報告書」の「SSP1-1.9シナリオ」に原則として準拠。 - ※4.0℃シナリオ
現時点で公表されている温室効果ガス削減に関する政策や目標の撤回を含めて、気候変動問題に対する有効な政策が実施されないシナリオ。
政策、エネルギー・産業構造、資源価格等は、IEA「World Energy Outlook2024」の「STEPSシナリオ」、平均気温等気候変動に関する想定は「IPCC第6次評価報告書」の「SSP5-8.5シナリオ」に原則として準拠。
<移行リスク>
国際的な気候変動対策の進展に伴い、カーボンプライシング(※)の導入・強化が多くの国で進められており、当社グループにおいても今後、各国の政策動向が財務に影響を及ぼす可能性があると認識しています。
IEA 「World Energy Outlook2024」のNZEシナリオでは、2030年の炭素価格が140ドル/t-CO2と予想されています。当社グループではこの価格をもとに、Scope1(直接排出)およびScope2(間接排出)の排出に伴うカーボンプライシングの財務影響額を、2030年度の以下の4つの売上高シナリオに基づき試算しています。

なお、この試算に用いた炭素価格やシナリオは今後のカーボンプライシングの動向に合わせて見直しを行い、さらなる温室効果ガス排出量の削減に取り組むことで、移行リスクの低減を目指します。
※カーボンプライシングとは、企業などの排出するCO2に価格をつけ、それによって排出者の行動を変化させるために導入する政策手法です。
<物理的リスク>
近年、日本国内では洪水や水害などによる浸水被害が甚大な経済損失を引き起こしており、これらは主要な物理的リスクとして認識されています。気候変動の影響により、浸水被害のリスクがさらに増大すると予測されており、企業の事業継続性を確保する観点からも浸水被害のリスクを検討することが重要です。
浸水被害のリスク検討の取り組みとして、国土交通省の「TCFD提言における物理的リスク評価の手引き」を参考に、建設現場を除く全事業所を対象として、「浸水ナビ」や「重ねるハザードマップ」を用いて洪水や高潮による浸水シミュレーションを行い、建物・在庫資産・償却資産への影響及び操業停止による売上高の減少を算出しました。この算出においては、将来の不確実な発生確率の仮定に依存せず、規模ごとの財務影響を可視化することを目的に、1/100、1/200、1/1000の複数の年超過確率(※)を用いて被害額を算定しています。
浸水被害のリスクが高い事業拠点においては、対策の優先順位付けとともに、防災・減災策の検討やBCPの見直しなどを通じて、気候変動に伴う物理的リスクへの対応を強化していきます。
※年超過確率とは、特定の規模を超える洪水等が1年間に少なくとも1回発生する確率。
リスク管理
サステナビリティ推進委員会は、当社グループ各社の取締役や経営幹部に対して意識調査を実施し、気候変動を含む幅広いサステナビリティ課題に対して高い関心を持っていることを確認するとともに、重要なリスクや機会を網羅的に抽出します。さらに、外部専門家の助言を活用し、専門知識に基づいた重要なリスクや機会の特定を行っています。
特定されたリスクや機会は、取締役会に報告され、審議・決定の対象となります。取締役会の関与により、組織全体のリスク管理の透明性と責任を確保しています。さらに、取締役会はリスクや機会への対応状況等のモニタリングを行い、適切な指揮・監督を行っています。
以上のようなサイクルを回すことで、変化する状況の中での新たなリスク要因や事業機会に対応するための努力を継続的に行っています。
指標と目標
当社グループは、気候変動に関するリスク・機会を管理するための指標として、環境負荷に関する重要な要素である温室効果ガス排出量を考えています。また、気候変動に対する取り組みを推進し、環境への影響を最小限に抑えるため、当社グループによる温室効果ガス排出量の削減に加えて、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組みも重要であると考えています。
GHGプロトコルの基準に基づき、2022年度を基準年度として、当社および連結子会社8社の直接排出(Scope 1)と間接排出(Scope 2)の排出量を算定しています。これを踏まえ、当社グループは温室効果ガス排出量削減目標として、2050年度までに実質ゼロ、2030年度までに2022年度比47%の削減(内訳:航空2社合計で4%削減、その他7社合計で70%削減)を設定しました。
排出量の算定および削減目標に基づき、使用電力のCO2排出量削減プランへの切り替えや太陽光発電システムの設置など、環境負荷の低減に向けた施策を実施しています。現在は、これらの取り組みをさらに加速させるための財務的影響について精査を進めています。
GHGプロトコルの基準に基づき、2023年度を基準年として、サプライチェーンを含む間接排出(Scope 3)の排出量も算定しました。その結果、当社グループのScope 3においては購入する鋼材に係る排出量が大きな割合を占めることが分かりました。この結果を受け、環境負荷を低減するため、高炉材よりもCO2排出量が少ないとされる電炉材の購入重量比率を重要な指標と掲げ、排出量削減の進捗を管理しています。
なお、現状Scope 3の削減目標は未設定ですが、今後SBT(※)認証取得を目指す中で、温室効果ガス排出量削減目標を設定する予定です。
※SBT(Science Based Targets)とは、世界の産業革命前からの気温上昇を2℃を十分に下回る1.5℃に抑えることを目指すパリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出量削減目標です。


- (注)当社グループはScope 1・ 2・3の排出量算出の精緻化に向けた取り組みを継続しています。
2023年度には、算定方法を理論値から実績値への見直しや現場で使用する重機の範囲を広げたこと、2024年度には工場で使用するシールドガスなどこれまで算定対象外だった排出源を新たに追加しました。これらの取り組みにより、Scope 1の「その他会社」を中心に排出量が増加していますが、これは実態に即したより正確な排出量を開示するためのものであり、排出管理の透明性向上を目的としています。なお、その結果を反映して2024年度の排出量を新たに算出し、2023年度のScope 3についても、より適正な数値に変更しました。
このように、当社グループでは、GHGプロトコルの基準に基づいた温室効果ガス排出量の算定と中長期的な温室効果ガス排出量削減目標の設定とその達成のための取組みを推進し、気候変動への対応を引き続き行っていきます。
事業に関するお問い合わせ、企業・IR情報に関するご質問はこちらより承っております。